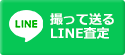近年、ニュースやSNSでも「スマートフォンの充電中に発火」「電動アシスト自転車が燃えた」といったバッテリー火災の話題を目にする機会が増えています。特にリチウムイオン電池は、スマホ・ノートパソコン・電動工具・電動自転車・モバイルバッテリーなど、私たちの身近な家電やガジェットに広く使われています。その便利さの一方で、扱いを誤ったり劣化したりすると火災につながるリスクをはらんでいます。
リサイクルショップとして多くの家電を扱う立場から言えるのは、「正しく使う意識」と「安全性の高い製品を選ぶ知識」が欠かせないということです。この記事では、実際の事故事例を交えながら、バッテリー火災が増えている背景と、安全に使うための注意点を解説していきます。
目次
リチウムイオン電池の仕組みと火災リスク
リチウムイオン電池は、小型ながら大容量の電力を蓄えられることから、スマートフォンやノートパソコン、電動自転車など幅広く利用されています。正しく使用すれば安全ですが、内部構造の特性上、発火や爆発のリスクを伴う点には注意が必要です。
過充電や衝撃で内部がショートする危険性
リチウムイオン電池は、プラス極とマイナス極を電解液で隔ててエネルギーをやり取りします。しかし、強い衝撃や過充電によって内部が損傷すると、電極同士が接触し「内部短絡(ショート)」が起こり、急激な発熱や発火につながることがあります。
経年劣化で発火リスクが高まる
長期間の使用で劣化が進んだバッテリーは、内部抵抗が増加し、充電や放電の際に通常よりも発熱しやすくなります。また、膨張や液漏れといった異常が現れるケースもあり、そのまま使い続けると火災につながる恐れがあります。バッテリーの寿命を過ぎたら、早めに交換やリサイクルに出すことが安全の第一歩です。
最近のバッテリー火災事例から学ぶ
リチウムイオン電池を搭載した製品は身近で便利な反面、取り扱いを誤ると火災の原因になることがあります。以下は、近年報道された代表的な事例です。
電動アシスト自転車のバッテリーから出火
2024年には、マンションの共用部で充電中だった電動アシスト自転車のバッテリーが突然発火しました。大きな人的被害はありませんでしたが、集合住宅における充電のリスクが改めて示されました。
モバイルバッテリーによる住宅火災
2025年には、就寝中に充電していたモバイルバッテリーが発火し、住宅の一部が焼損する火災が発生しました。調査ではPSEマークのない製品であることが判明し、安全な製品選びの重要性が浮き彫りとなりました。
新幹線内でのバッテリー発火事故
2025年8月28日、上越新幹線(東京行き)車内で、スマートフォン用バッテリーがかばん内で発火し、持ち主の男性が軽いやけどを負う事故がありました。男性はズボンで火を覆って消火し、他にけが人はいませんでしたが、一部の列車が遅延する事態となりました。
さらに、2025年8月下旬には中央日本方面の別の新幹線でも、モバイルバッテリーが発火したケースが報告されており、こちらは乗客にけがはありませんでしたが、列車が一時停止したとされています。
海外製格安バッテリーによる事故
通販などで簡単に手に入る安価な海外製バッテリーや充電器も、内部保護回路が不十分な場合が多く、過熱や過充電時に安全装置が働かず、発火事故を引き起こすことがあります。消費者庁や消防庁も注意喚起を行っています。
安全な製品の見分け方
リチウムイオン電池を安全に使うためには、そもそも「信頼できる製品」を選ぶことが重要です。安価な製品の中には、基準を満たしていないものが流通している場合もあり、火災のリスクを高めてしまいます。ここでは、家電のプロの視点から安全な製品を見分けるポイントを紹介します。
PSEマークを必ず確認する
日本国内で販売される電気製品は、法律に基づき「PSEマーク」の表示が義務付けられています。これは電気用品安全法に適合していることを示すマークで、正しく検査された製品である証拠です。PSEマークがないバッテリーや充電器は安全性が確認されていないため、購入を避けるべきです。
説明書や保証の有無をチェック
正規品であれば、日本語の説明書や保証書が付属しているのが一般的です。こうした付属品がない製品や、販売元が不明確な商品は注意が必要です。アフターサポートがしっかりしているかどうかも安全性の目安になります。
安価すぎる海外製品に注意
インターネット通販などでは、見た目が似ていても極端に安価な海外製バッテリーや充電器が販売されています。内部の保護回路が不十分な場合が多く、過充電や異常発熱の際に安全装置が働かず火災に至るケースがあります。価格だけで選ばず、安全基準を満たした製品を選ぶことが重要です。
バッテリー火災を防ぐためにできること
リチウムイオン電池は正しく扱えば安全に使えます。日常生活で少し注意するだけでも、発火や事故を防ぐことができます。ここでは家電のプロの視点から、すぐに実践できる予防策を紹介します。
正規の充電器・バッテリーを使う
必ず製品に対応した純正の充電器や正規品のバッテリーを使用しましょう。互換品や安価な充電器は内部の制御回路が不十分な場合があり、過充電や過熱による火災のリスクが高まります。
充電中は目を離さない
就寝中や外出中に長時間充電しっぱなしにするのは危険です。充電はできるだけ目の届く場所で行い、異常があればすぐに対応できるようにしましょう。
発熱・膨張・液漏れを感じたら使用中止
使用中にバッテリーが異常に熱を持ったり、膨らんだり、液漏れした場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると発火の危険があります。
不要になったバッテリーは正しくリサイクルへ
寿命を迎えたバッテリーは、自治体の回収ボックスやリサイクルショップに持ち込みましょう。ごみと一緒に捨ててしまうと、収集車内や処理場で発火する事故につながります。リサイクルに出すことが安全にも環境にもつながります。
不要になったバッテリーの正しい処分方法
リチウムイオン電池やモバイルバッテリーは、普通ごみや不燃ごみと一緒に捨てることはできません。誤った処分は収集車や処理施設での火災につながる恐れがあります。ここでは安全で正しい処分方法を紹介します。
家電量販店やリサイクル協力店に持ち込む
日本では「小型充電式電池リサイクル(JBRC)」の仕組みにより、家電量販店やホームセンターなどに専用の回収ボックスが設置されています。対象のリチウムイオン電池やモバイルバッテリーは無料で回収してもらえます。
自治体の回収サービスを利用する
自治体によっては「小型家電リサイクル」や「有害ごみの日」でバッテリーを回収しています。ただしモバイルバッテリーが対象外の場合もあるため、事前に自治体のホームページで確認しましょう。
リサイクルショップや専門業者に相談する
リサイクルショップや電気工事店などで、不要なバッテリーの処分や下取りに対応している場合があります。家電と一緒にバッテリーを処分したいときは相談してみると安心です。
一時保管の注意点
- 端子部分をビニールテープなどで覆い、ショートを防ぐ
- 金属や可燃物から離れた場所に置く
- 膨張や液漏れがある場合は、金属缶などの耐火容器に入れる
やってはいけない処分方法
- 燃えるごみ・不燃ごみとして出す
- 金属ごみと一緒に廃棄する
- 水に浸したり冷蔵庫に入れて保管する
正しい方法で処分することが、自分自身の安全を守るだけでなく、収集や処理に携わる人々を守ることにもつながります。
万が一火災が起きてしまったら
どれだけ注意していても、バッテリー火災が起きてしまう可能性はゼロではありません。万一の事態に備え、正しい対応を知っておくことが大切です。
初期消火に有効な消火器とは
リチウムイオン電池の火災には、一般的な「粉末消火器」や「二酸化炭素消火器」が有効です。家庭用に備える場合はABC粉末消火器を用意しておくと安心です。
水をかけてよい場合・悪い場合
バッテリー単体の火災であれば、水をかけても問題ないとされています。ただし、通電中の機器に水をかけると感電や拡大のリスクがあるため注意が必要です。基本は消火器を使い、難しい場合はすぐに避難してください。
換気を行い煙を吸わない
バッテリーが燃えると有害ガスが発生することがあります。無理に煙を吸い込むと健康被害につながるため、可能であれば窓を開けて換気しつつ、速やかに避難しましょう。濃い煙が充満している場合は姿勢を低くして移動することが重要です。
やってはいけない誤った対応の事例
もしバッテリーが膨張し始めたとき、「冷蔵庫や冷凍庫に入れれば」と考えてしまう方もいるかもしれません。確かに発熱したものを冷やすという考えは合理的に感じるかもしれませんがこれは非常に危険です。
- 極端な低温環境は化学反応のバランスを崩し、発火や爆発のリスクを高めます
- 冷蔵庫内の温度差により結露が発生し、ショートの原因になることもあります
- また、EPAなどの公的機関も「冷蔵庫に入れる必要はなく、むしろ避けるべき」と推奨されています
膨張したバッテリーはすぐ使用を中止し、不燃性の容器に入れて短期間保管するか、自治体や専門のリサイクル窓口へ速やかに持ち込みましょう。金属缶や砂入り容器を使うのが安全です
まずは避難と119番 ― 命を最優先に
火の勢いが強くなったら、自力での消火は危険です。迷わず避難し、119番通報してください。バッテリー火災は急激に広がることがあるため、命を最優先に行動することが何よりも大切です。
まとめ ― 安全に家電を使うために知っておきたいポイント
バッテリー火災は、スマートフォンや電動アシスト自転車、モバイルバッテリーなど、私たちの生活に身近な製品で発生しています。便利な一方で、使い方や製品選びを誤ると重大な事故につながることがわかりました。
- リチウムイオン電池は過充電・衝撃・劣化で火災リスクが高まる
- 最近では住宅や新幹線内など、身近な場所での発火事例も増えている
- PSEマークの有無や保証の有無を確認し、安価な粗悪品は避ける
- 充電中は目を離さず、異常(発熱・膨張・液漏れ)があれば使用を中止する
- 不要になったバッテリーはごみと一緒に捨てず、正しくリサイクルする
- 火災が起きた場合は消火器を使用し、換気・避難を最優先にする
- 膨張したバッテリーを冷蔵庫に入れるなどの誤った対応は危険
日常のちょっとした注意や製品選びで、バッテリー火災のリスクは大きく減らせます。家電のプロとしては、「安全第一で使う」意識を常に持ち、もし異常を感じたら早めに専門の窓口へ相談することを強くおすすめします。
バッテリーや家電は、長期保管しているうちに劣化が進み、処分に困ってしまうことも少なくありません。不要になった時点でリサイクルショップに売れば、まだ商品価値があるリユース品として引き取ってもらえ、お金にもなります。賢く安全に手放すことで、火災リスクを防ぎながらお得にリユースが可能です。